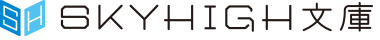薔薇コミュニケーション
ゴールデンウィーク明けの放課後、図書委員であるわたし、
モデルとなっているのは、幼馴染でありトラブルメーカーとして有名な
小さな事件の連鎖と、青春とは何かと問うような絵画についての謎、歪曲されたジンクスの真相などなど、二人から聞いたことが今回の小説のネタだ。
しばらく、そんな小説の構想を夢中になって書いていたら、
「四宮、お疲れ様」
と声をかけられた。
顔を上げるとそこには、同級生の
「勘違いしないでよ?」 「え?」 「自分用じゃないからね。後輩に教える参考になればいいなぁと思って」 「ああ、なるほどね」 「美術部の新入部員がさ、漫画を描きたいんだって。それは別にいいんだけど、人体の描き方を知りたがっていたから、上手く教えてあげられないかなと思って借りただけだから」
初心者向けの本を借りていた、というのが気恥ずかしいのだろう。面倒見が良いね、とわたしは笑みを返す。
「違うわよ。高校生活で美術部に入ろうって思ってくれたなら、楽しんでもらいたいじゃない」
「それを面倒見が良いって言うんだよ」
むっつりとした表情をさせていた似鳥さんの顔が赤くなる。彼女はいつも気難しげな顔をしているし、言動に棘があると感じる人も多いようだけど、本当は優しい人だということをわたしはちゃんと知っている。
わたしの所属している文芸部にも後輩が入ってくれたけど、なにをしてあげられるかなあと思いを巡らせる。以前新入部員に「四宮先輩はどうやって物語のインスピレーションを得てるんですか?」と尋ねられ、白亜ちゃんと深緑さんのことを思い浮かべたが、企業秘密だと誤魔化した。
一人でくすりと笑っていると、「なに笑ってんの?」と似鳥さんが怪訝そうに声をあげた。
なんでもないよ、とかぶりを振りながら、似鳥さんがまだいたことに少し驚く。本の返却手続きは済んでいるのだが、帰ろうとしない。眉を歪め、何か言いたげな顔をして立っていた。
「どうしたの?」
「あのさ、四宮はアイツと仲が良いじゃん?」
「アイツ? 白亜ちゃんのこと?」
似鳥さんは、白亜ちゃん絡みのトラブルに何度も巻き込まれたことがある。もしかして、と思って彼女の名前を出してみたのだが、どうやら当たりだったようだ。
「そう。先月、ちょっと美術部で事件があってさ、アイツのことを悪く言っちゃったのよ」
言い淀む似鳥さんを見ながら、その事件のことは二人から聞いていたな、と思い出す。美術部で起こった油絵道具盗難事件のことだ。似鳥さんが勘違いをして、白亜ちゃんを犯人扱いしてしまった、というあらましだ。
「新入部員の指導もさ、それの責任を感じてやってるんだよね」
「責任?」
「私が騒いじゃったせいで部の空気を悪くしちゃったのよ。それで汚名返上しないとなぁと思って」
似鳥さんが堅い表情でそう言ってから、「話を戻すね」と説明を続けた。
「四宮、アイツにそれとなく私が悪いと思ってたって伝えておいてくれない?」
「自分で『ごめんね』って言うのが一番だと思うよ」
「嫌! それだけは嫌! 今までにされたことを考えたら!!」
相変わらず仲が悪いなあ、と苦笑する。
「わかった、それとなく伝えてみる」
「ありがとう四宮」
そう言って、似鳥さんは図書室を後にする……と思っていたのだが、まだカウンターの前に立ち、もじもじとしていた。
「どうしたの?」
「実はさ、もいっこ相談したいことがあるんだけど、話聞いてくれない?」
「いいよ。どうしたの? 白亜ちゃん関係?」
「アイツはもう関係ないよ。実は部活でさ、変なことがあって」
変なこと? と口にし、少し胸が弾む。物語のネタになるかもしれないと感じて、シャーペンをかちりとノックする。
「一年生の教員室前の廊下に、これから月替わりで美術部員の絵を飾っていこうっていう話になってるのよ」
「そうなんだ、良いアイデアだね」
「思いつきで顧問に提案したら、オッケーされたんだよね。それでさ、四月とゴールデンウィーク中、部員六人みんなで油絵を描いてたのよ」
「切磋琢磨してる感じでいいなあ」
「それがいいことばかりじゃなくてさ、誰の絵を飾るか? っていうちょっとしたコンクールみたいになってて。私派か
「そこは部長の似鳥さんの絵で良いんじゃないの?」
と提案する。
「そういう理由はフェアじゃないから嫌」
「真面目だねえ」
「良い絵を飾りたいだけよ。絵の展示は新入生に向けてのアピールにもなると思ってるんだよね。美術部に入るとこんな絵が描けるようになるのか、みたいな。まだ五月だし、部活決めてない子もいると思うから」
「そうなると、最初に展示される絵は、やっぱり一番上手い絵が良いね」
「でしょ? それで、三年の小田原先輩か私の絵にするかって感じで、ちょっとギスっててさ。言いにくいんだけど、私と小田原先輩って反りが合わないのよねぇ」
「それを丸く収める相談ってこと?」
「違うのよ、本題はこれから」
確かに、部活の人間関係だけでは「変なこと」とは言わないな、と思い直し続きを促す。
「美術部の部室には絵のモチーフにするための小物が入ってる棚があるの。ワインボトルとかプラスチックの果物とかそういうのね」
はいはい、と相槌を打つ。美術室の後方には石膏像の入った棚があるけど、そういう小物は部室にあるのか、と知識を得た。
「私が描いてる手のデッサン模型もそこにあるんだけど、絵を描く準備をしようと思って棚を開けたらさ、その手が造花の赤い薔薇を握ってんの。これってどういうことだと思う?」
「造花の薔薇? 小物がごちゃっと置かれて、そうなっちゃったとか?」
「棚の中には造花ゾーン、模型ゾーン、果物ゾーン、みたいになんとなく分けられてるし、私も最初はたまたまかなって思ってたんだけど、一度や二度じゃないしね。なおさら不可解なの」
「誰かが、似鳥さんが使ってる手だって知ってて、意図的に薔薇を握らせてるってこと?」
「そうとしか思えないのよ」
手のデッサン模型が握っていた造花の薔薇、これは一体どういうことだろうか? 深緑さんではないけど、この不思議な出来事にますます興味が湧いてきてしまった。
とっさに、頭の中でロマンチックな考えが
「誰か男の子が似鳥さんを応援してるのかもしれないよ?」
「なんで男子が?」
「それはほら、薔薇の花言葉。『愛情』『情熱』『あなたを愛しています』ってね」
自分で言っていて恥ずかしくなってしまった。対する似鳥さんも耳まで顔を真っ赤にしていた。
我ながら乙女な思考だなあと思う。でも白亜ちゃんはちょっぴりがさつだし、深緑さんは男子だから、きっと二人では思い浮かばないことだろう。
「ない! それはないって!!」
「えー? わからないよお?」
にやにやしながらそう告げると、「男子は二人しかいないから、
油絵道具盗難事件のことで話を聞いていたから、美術部員のことはなんとなく把握している。吉野さんは痩せた眼鏡の男子で、藤さんは深緑さんの同級生だ。迷惑とはどういうことか? と首を傾げる。
「その薔薇、小田原先輩が絵のモチーフにしてるのよ。それをいちいち造花ゾーンに戻すわたしの身にもなってほしいわ」
「思いは伝わらないねえ」
「悪いけど、やっぱり違う気がするよ。二人からそんな恋愛オーラ出てないし。こう見えて私、そういうの敏感なんだよね」
そうなると真相はわからないなあ、とわたしは唸った。
似鳥さんはわたしに話をしたことで少し満足したのか、「真相が分かったら連絡ちょうだい」と言って去って行った。
「四宮さん、こんにちは」
「赤音お疲れー」
ノートから顔を上げると、そこには白亜ちゃんと深緑さんのコンビが立っていた。
深緑さんはゴールデンウィーク中に散髪をしたのか、髪が前より爽やかな感じになっている。対して、白亜ちゃんは相変わらず天然のふわっとした髪型をしている。彼女の、一癖あるという感じが髪型に表れているなあ、といつも思う。
「はいこれ、返却」
白亜ちゃんがわたしに本を差し出す。それは宇宙人や超能力についての本だった。怖い話が苦手のくせに、そういう系の話は好きだよねえと思いながら、「さっきまで、似鳥さんがいたんだよ」と教える。
「マジかよ。セーフだな」
「そんな嫌そうな顔をしないの」
そうたしなめながら、「そうそう」と話を切り出す。
「似鳥さんから伝言。パレットの件、『悪いと思ってた』だって」
ごめんなさいと伝えて、と言われたわけではないので、わたしはそのままを伝える。白亜ちゃんは不機嫌そうに下唇をぬっと突き出した。
「あの件ですか! 僕も気になってたんですよ。あれは冤罪なんですから」と深緑さんが白亜ちゃんの代わりに怒り、腕を組んだ。
「謝られてもなんだか気まずいんだよ」
「謝られてはいないじゃないですか」
「謝りたそうにしていただけだね」
白亜ちゃんが、面倒臭いねぇ、とかぶりを振る。
謝罪をされてもそれはそれで嫌だ、と思っているようだ。わたしは『仲直りできない人っているよね』くらいに思ってもいるけど、意外と将来、二人が仲良くなったりなんかして、と妄想を膨らませてもいた。
「あの件のおかげで色んなことがわかったし、気にしてないんだけどねぇ」
「先輩も似鳥さんに『気にしてないよ』って言ったらどうですか?」
「絶対に嫌だね」
「似鳥さん、きっと気にしてると思いますよ」
白亜ちゃんが口を横に伸ばし、心底嫌そうな顔をする。
「白亜ちゃん、似鳥さんに何か伝えておく?」
「なんの件でしょうか? って伝えといてくれよ」
「それだと余計こじれますって」
「ほうら、面倒臭い。いいんだよ、似鳥は私からの反応なんて求めてないって」
「仲が良いんだか悪いんだかわからないですね」
「仲は悪いよ」
二人のやり取りを見ながら、すっかりコンビ然としてきたなあと頬が緩む。
ちょうどいいタイミングで二人が来たので、先程の似鳥さんから聞いた美術部の話をしてみようと思いついた。
「似鳥さんから不思議な話を聞いたんだけどね」
不思議な話? と首を傾げる二人に、美術部の絵の展示の話と、誰かが似鳥さんに薔薇を使ってコミュニケーションを図ろうとしている話をした。
好奇心旺盛な深緑さんは、ふむふむと頷き、「展示はいつからなんですか?」とか「部長の絵じゃだめなんですか?」とか「部員は何人なんですか?」とか「男子は何人ですか?」と色々質問をしてきたので、知っていることを伝える。
「美術部の部室は普段鍵が掛かっているから、一般生徒じゃ無理でしょうね。となると、藤、なのかなあ?」
わたしが話を伝え終えると、深緑さんがぽつりとそうこぼした。
「なんで藤さんだと思うんですか?」
「赤い薔薇の花言葉は、『あなたを愛している』ですからね」
深緑さんたら意外と乙女! と思わず口に手をやる。
「お前、そういうこと言って恥ずかしくないのかよ?」
「だんだん恥ずかしくなってきました」
「藤ってやつはそんなキザな真似をできる奴なのか?」
尋ねられ、深緑さんがむーんと唸り、「思えないですねぇ」と呟いた。
「てっきり絵を教えてもらってる内に惚れたのかな、と思ったんですけど、そんな度胸がある奴じゃないですね。四宮さん、美術部って男子は藤以外だと、吉野さんだけなんですよね?」
「はい、確かそのはずです」
「じゃあ、その吉野さんがやったってことですか」
「いや、そもそも薔薇で告白するって発想がやばいっつうの」
深緑さんとわたしの乙女心が、一笑に付された。他人事だったから盛り上げてしまったけれど、自分がされたらどうか? となると、やっぱり「回りくどい」と思ってしまうだろう。それに実際にやられたとしたらちょっと怖い。
「先輩、その行為の意味が『告白』じゃないとすると、その絵の展示についてですかね」
「だろうねぇ」
「似鳥さんか小田原さんかってなってるんですよね。だったら、部員の誰かが『自分は似鳥さんの方が良いと思う』っていうのを間接的に伝えるために、薔薇を移動させてるんじゃないですか? 応援してますよ! 的な意味で」
深緑さんが口にし、自分の言葉に納得した様子で、うんうん頷いた。わたしも、愛の告白よりもそちらの方が妥当だなと思い、シャーペンを走らせる。
が、「ないな」と白亜ちゃんが首を横に振った。
「なんでそう思うんですか?」と深緑さんが口を尖らせる。
「お前、そんなことをしたら、部の空気が悪くなるだろ?」
確かに。二人の仲は良くないらしいから、小田原さんが棚を開けたとき、自分が使っている薔薇が似鳥さんが使っている手に何度も握られていたらいたら嫌な気持ちになるだろう。他の部員がそれに気づいたら、何か不穏な感じがする、と考えを巡らせるかもしれない。
「先輩、空気とか読めたんですね」
「お前は大概失礼なやつだな」
本気でびっくりしました、と深緑さんが口にすると、白亜ちゃんに脇腹を小突かれていた。
「白亜ちゃん、空気が読めない人が犯人ってことはない?」
「それよりも、もっと合理的な説明がつくよ」
「え? 先輩、何かわかってるんですか?」
そらそうよ、と白亜ちゃんが胸を張り、私と深緑さんは目を剥いた。
「これはコミュニケーションの問題だね。私と似鳥が良い例じゃないか」
「どういうこと? ちゃんと教えて」
「直接言うのはなんとなく嫌だから、回りくどーく伝えようとしたんだよ」
「薔薇で何を伝えたかったんですか?」
深緑さんが白亜ちゃんに詰め寄る。私も、知らず知らずカウンターから身を乗り出していた。
「現象の通りのことだよ。手のデッサン模型が薔薇を握ってるんだろ? そういうこと」
「どういうこと?」
「花を持たせる」
白亜ちゃんがそう言い切り、わたしは「あー」と嘆息を漏らしながら椅子に座り直した。それなら、空気が読めない人説よりもちゃんと説明がつく。
花を持たせる、『人に名誉を譲る』『その人を立てて功を譲る』という意味だ。
「つまり、花を移動させているのは小田原先輩本人ってことですね?」
と深緑さんが白亜ちゃんに確認する。白亜ちゃんが大きくうなずいた。
「小田原って先輩と似鳥は仲が良くないんだろ? 似鳥は盗難事件があって後輩や部員の前で恥をかいてしまった。それを挽回しようと頑張っているみたいだし、その先輩は評価してやりたいと思ったのかもしれないな」
「でも先輩、美術部としては新入生に良い絵を見せて美術部に興味を持ってもらう方が大事じゃないですか?」
「小田原さんからしたら、悔しいけど似鳥の方が上手いって思ってるのかもしれないぞ。部員の数も偶数だし、どちらの絵を飾るか投票で決めるにしても半々になったらややこしくなりそうだ。だから、早めに伝えたいと思ったのかもな」
白亜ちゃんからの説明を受け、今度は納得した様子で深緑さんは大きく頷いた。
そんな二人のやり取りを眺めながら、バッグからスマートフォンを取り出す。似鳥さんに「花を持たせるって意味だと思うよ!」という旨のメッセージをそっと送った。白亜ちゃんが推理した、ということは伏せておく。きっと苦虫を噛み潰したような顔をしてしまうだろうから。
これも物語のネタになるなと思いながら、そうだ、と思い出す。
「お二人はゴールデンウィークの間、何をしてましたか?」
なんの気なく尋ねたのだけれど、深緑さんがかっと目を見開いて白亜ちゃんを見た。
「よくぞ聞いてくれました。大変な目にあったんですよ。先輩のせいで死にかけたんですから!」
「詳しく聞かせて下さい!」
これは長いお話になりそうだ。机の上の私物を急いでバッグにしまい、司書さんに「今日はこれで失礼します」と声をかける。
「死にかけたとは大袈裟な」
「どの口がそんなことを言うんですか」
「か弱い乙女のこの口だよ」
「どの口がそんなことを言うんですか」
「だから、この口だよ!」
仲睦まじく言い合う二人を眺めながら、今回も見事な推理だったなあ、と感心する。不思議な出来事の謎を解く、それはわたしにはできなかったことだ。わたしと彼女たちとは違う。
人は、プレイヤーとサポーターの二種類の人間に分けられる。
これは他の誰でもない、わたしの言葉だ。トラブルに立ち向かって解決できる人と、彼らを応援する人に分けられるのではないか、と日々感じている。
彼女たちはプレイヤーだ。
トラブルメーカーの白亜ちゃんは、昔からいくつもの事件やトラブルを引き起こしたり、巻き込まれたりしている。それを間近で見ていたわたしは、どうしたら彼女の助けになれるか? と苦心していた。
でも、できなかった。
無力感に襲われる日々を過ごしていたのだが、深緑さんが現れてからは一変した。深緑さんはトラブル解決に協力的だし、白亜ちゃんの推理の呼び水になっているようだ。
白亜ちゃんは、前より生き生きしている。それは、彼女の隣、わたしでは収まれなかったポジションにいる深緑さんのおかげだろう。
わたしはそんな二人のサポーターになろうと決め、サポーターにしかできないことをしようと思うようになった。
例えば、二人の活躍を記録し、物語にして伝えることは、わたしにしかできないはずだ。
カウンターから出て「はいはい、屋台に着いたら聞きますから」と声をかけると、二人はようやく口論をやめた。
「赤音にジャッジしてもらおう」
「のぞむところですよ」
「お任せ下さい。わたしはお二人のサポーターですから」
きょとんとする二人を押し出すように、図書室を後にする。
前を歩く深緑さんが隣の白亜ちゃんに向かって口を尖らせ、白亜ちゃんがそれをいなしている。これから、どんなお話を聞かせてもらえるのだろう、と期待に胸を膨らませながら二人を眺める。
すると不意に白亜ちゃんが立ち止まり、振り返った。
「赤音、あんたは私の友達だよ」
矢のような言葉に貫かれ、思わず立ち止まってしまう。一方の白亜ちゃんは、さっぱりした口調と同様に、何事もなかったかのように歩き出していた。
白亜ちゃんにはまいったなあ、と小さく笑う。わたしの負い目も見抜かれていたようだ。
校門へと続く、すっかり花をなくした桜並木の間から夕日が差し込み、道が照らされている。少しだけ眩しくて、なんだか暖かい。
この気持ちはどんな物語にできるのかな?
そんなことを考えながらわたしは二人の隣に並んだ。
了