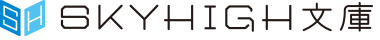てのひらの夏に咲く
夏休みも残すところあと三日。宿題に行き詰まった俺・
店へ着く頃には、容赦なく照りつける暴力的な太陽光線に、外へ出たことを心底後悔していた。でも、涼しい店内でアイスを選んでいると段々気分が晴れてくる。
このまま、英語の長文読解ワークも、白い所がずいぶん残った風景画の下描きも、いっそ忘れてしまいたい。この二つが終われば、夏休みの宿題から解放されるんだけど、最後まで残ってしまっているだけあって手ごわかった。
(……とりあえず、今はアイス選ぼうっと)
部屋に残った宿題のことは脳内から押し出して、俺はアイスケースをのぞきこむ。アイスの種類が豊富と評判のコンビニなだけあって、いろんなアイスが並んでいる。
フルーツ系がいいかバニラ系か、それともチョコレートか。財布の中身と相談しながら真剣に選んでいると、ポケットに突っ込んでいた携帯電話が震えた。ブブブ、という振動に、慌てて携帯電話を引っ張り出す。表示された相手の名前を確認してから通話ボタンを押すと、明るい声が飛び込んでくる。
『園田、今日ひま?』
耳元で弾けるような声は、
「え、うん。今コンビニにいるけど……よくわかったな」
『声がちょっと聞き取り辛いからそうかなって。駅前のコンビニ?』
「そう。アイスの種類多いじゃん?」
『わかった! じゃあ、今行くから待ってて! 僕も駅前のスーパーにいるの!』
一言叫ぶと、俺の返答を聞く前に通話が切れた。無音になった携帯電話を思わず見つめてしまうけど、何の反応もあるわけがない。こうなったら、俺はコンビニで成島が来るのを待つしかなかった。帰ったところで宿題がはかどるわけじゃないし、コンビニなら涼しいし、まあいいか。
ひとまず雑誌の棚に移動して、週刊の漫画雑誌を手に取った。パラパラとめくりながら考えるのは、必然的に電話の主――成島のことだ。
連鎖的に思い出すのは、二人の人物だった。
勉強はできるけどいつもツンケンしてて口が悪い、眼鏡と眉間のしわが標準装備の
クラスは一緒だけど、接点なんて全然なかった。だけどこの夏、俺が一番顔を合わせているのはこのメンバーだと思う。
きっかけはほんの一ヵ月ちょっと前。夏祭りを控えた終業式の日、居残りを命じられた俺たち四人は、夜の学校に閉じ込められたのだ。
どうにか脱出しようと試すうちに、お互いの知らなかった顔を知った。何でもない話をして、少しずつ心の内側を知った。そうして過ごした祭りの夜は、気づけば今日につながっている。
終業式の日のこととか、仁羽が親戚から押しつけられたスイカを、みんなで食べた夏休み頭のこととかを思い出していたら、コンビニの自動ドアが開いた。反射的に目を向ければ、待ち人が入ってくる。
「――成島」
雑誌を置いて駆け寄ると、麦わら帽子を脱いだ成島がぱっと笑顔を浮かべた。
普段はふわふわの前髪がぺったりと汗で額に貼りついていて、外の暑さをものがたる。成島は大きな布の鞄を持っていて、肩からはかぎ編みのポシェットを掛けていた。十中八九、中にはメノウ様がいるんだと思う。見つめていたら、成島に「アイス買った?」と聞かれたので首を振る。
「まだ。成島も食べる?」
「うん! 何にしようかなぁ」
店内に飲食スペースもあるのでそこで食べていこう、と言い合いながらアイスコーナーへ向かう。アイスケースをのぞきこむ成島に、俺は質問を投げた。
「――で、何か用あったんだろ?」
そうでなきゃわざわざ来ないだろうし、と思っていると、成島は真っ直ぐ俺を見て言った。きらきらとした笑顔を浮かべて、店の中まで太陽を連れてきたみたいな顔で。
「うちで花火やろ! 四人で!」
言って、大きな鞄を広げる。そこには市販の花火セットが入っていた。
「……もしかして、これ買いにスーパーに来てたとか?」
「そう。メノウ様と一緒に選んだんだよねー」
そう言ってポシェットを開けば、予想通りメノウ様が鎮座していた。語りかける横顔は、完全にウキウキしている。
俺が返す言葉を探している間に、成島はカップのバニラアイスを選んでいた。そのままレジに向かっていくので、俺も慌ててあとを追う。散々悩んだけど、結局ソーダ味の棒アイスにした。
会計を済ませて、店内の飲食スペースへ向かう。誰も居なかったので、成島と隣同士で奥の席に座った。一つ息を吐いた俺は、カップの蓋を開けている成島に向かって口を開く。
「花火、誘ってくれるのはすげえありがたいんだけど、俺まだ宿題終わってなくて。これからラストスパートっていうか、宿題終わらないと出かけられないそうにないから、花火やるのはちょっと難しいかも」
成島はぱちぱちと目を瞬かせていて何も言わないので、さらに言葉を続ける。
「宿題も終わってないのに遊びに出かけるとか、許してくれないと思う」
今年は終業式の日の一件で家族や学校に迷惑かけたから、余計にその辺は厳しそう、というのは黙っておいた。ただ、話をここで終わらせるのも気まずいから、俺はなるべく軽い調子で言葉を続ける。
「つーか、成島は宿題終わってんの?」
「終わってるよ!」
スプーンを手にした成島に即答された。マジで。もしかしたら仲間かも、と思ってたのに。
「すごいな!?」と思わず感想を漏らしたら、成島は弾んだ声で教えてくれた。
「うん! 自由研究とかね、すっごく頑張ったんだよ! メノウ様の歴史をまとめたんだ!」
「……」
自由研究って理科分野対象じゃなかったっけ。なるほど、成島はちゃんと提出物とかは出すけど、方向が斜め上のタイプだったか。思わず黙り込んでいると、成島は明るい声で尋ねた。
「園田は何が終わってないの?」
「えー……英語の長文読解ワークと、美術の風景画」
アイスの袋を開けつつ答える。一番苦手な読書感想文が今年は終わっているのは、仁羽のアドバイスがあったからだ。せめてあれは終わっててよかった、と思っていると成島が、言葉の一つ一つが弾んでいるような、楽しくって仕方ないって声で言った。
「じゃあ、終わらせちゃって一緒に花火やろ!」
とんでもなく素晴らしい思いつきをしたっていう顔で成島は言う。
「だって、園田がいなくちゃだめだって、メノウ様も僕も仁羽も遠山も言うよ」
光の塊みたいな、強い輝きを放つ声で。成島は力強く、宣誓するみたいに言い切った。
「宿題全部終わらせて、みんなで花火やろ!」
俺は一瞬言葉を忘れた。だけど、すぐに理解する。
どんな言葉が正しいかなんて、もう考えなくたっていいんだ 。俺は短く息を吸って、吐いて、心のままに言葉を落とす。
「――うん。俺も花火、やりたい」
こうなったらサクサクと終わらせて――できるかどうか微妙だけど頑張らないと、という気持ちで告げたら、成島はあっけらかんと続けた。
「じゃあ、うちで宿題やろうよ!」
「え、待って。今そういう話だった?」
思わず聞き返すと、スプーンでバニラアイスをすくっていた成島が、不思議そうな顔で答える。
「だって、花火やるのうちだし、風景画なら僕も手伝いできると思うし。英語のワークだって、仁羽がいれば早いでしょ?」
わかりきったことを説明するみたいな口調だった。俺はしゃくしゃくとソーダアイスを頬張りつつ聞いていたが、説得力はあった。確かに、現役美術部員の成島と学年一位常連の仁羽は、強力な助っ人だ。
「遠山も呼んだら来ると思うし。二人にも連絡しておくから、うちにおいでよ。花火やるから友達来るんだって言ってあるから、準備万端だよ!」
「え、と、いいの?」
助けがあるのは正直ありがたい。けれど、迷惑じゃないかな、という意味で尋ねると、成島は大きくうなずいて言った。
「もちろん! 早く終わらせて、みんなで花火やろうね!」
どうやら、成島にとっては四人そろって花火をやることが決定事項らしかった。こうなった成島は止まらないだろうし、俺だって異論があるわけじゃない。なので「お願いします」と言えば、成島は満足そうにバニラアイスを食べながら楽しそうな声で答えた。
「じゃあ、一時間後にうちに集合ね!」
「オッケー。でも、あの二人来られるのかな」
当然のように話が進んでるけど、用事があるって可能性もあるだろう。しかし、成島はやけに確信めいた口調で言った。
「大丈夫。ちゃんと全員集合するよ! だってメノウ様が言ってるもん」
「なるほど」
メノウ様のお告げならきっと間違いないんだろう。思いながら、俺は残り少なくなったソーダアイスを口に放り込んだ。
結論から言えば、メノウ様のお告げは正しかった。約一時間後、成島の家には四人が揃ったのだから。
「園田、ちゃんと来られてよかったね!」
コンビニで別れる前、ちゃんと親を説得できるよう祈っててくれ、と言ったのを覚えていたらしい。出迎えてくれた成島は笑顔を浮かべて言う。
「メノウ様のおかげかな!」
「うん、そうかも。あと、学年一位は効いたっぽい。仁羽ありがとう」
肩からバッグをかけた仁羽にお礼を言うと、「別に礼を言われることじゃねえ」と返ってきたけど、実際問題、仁羽の効力は大きかったと思う。「学年一位に勉強教わってくるから」と言ったら母親の態度が軟化したし、夜の外出も許してくれた。
「それじゃあ、ぱっと終わらせちゃおうね!」
そう言いながら成島が案内してくれたのは、裏庭に面した和室だった。障子も窓も全開にしてるから、外の風が入ってくる。周囲にある木のおかげか、家が山のほうにあるからか、少し気温も低いような気がした。
真ん中に置かれた机を挟んで座り、鞄を探る。慌てて宿題一式持ってきたから数学のワークとかも入ってたけど、今は必要ない。俺は美術の課題と英語のワークを広げた。
「……そういえば、二人とも予定とか平気だったんだな」
ペンケースとかを取り出しながら、向かいに座っている仁羽と遠山に向かって聞いてみた。仁羽はペラペラと俺の英語読解ワークを一通り眺めてから、答えを返した。
「宿題なんざとっくに終わってるからな。お前の相手をする余裕はある」
「俺は……呼び出されれば……どこでも行くよ……?」
ものすごく行動力のある人間みたいな答えを返したのは遠山だけど、どういう意味かはよくわかっていた。仁羽が茶化すような雰囲気で言う。
「妹にひっつかれるのが迷惑だから出て来てるだけだろ」
仁羽の言葉に、俺の正面に座っていた遠山は重々しくうなずくと、同じ調子で言葉を落とした。
「……家にいる限り……ついて来られるからね……」
遠山の妹は、終業式の日以降ずっと遠山にべったりだと聞いている。家の中ならトコトコ後ろをついてくるし、隙あらば背中に乗っかって遊ぼうとするという。出かけようものなら泣き出すというのは、実際に目の当たりにしたこともある。
遠山自身は、妹に対して複雑な感情を抱いているのは知ってたから、てっきり妹もそういう感じだと思ってたんだけど。そういうわけでもないらしい。
「お兄ちゃん大好きだよねぇ」
にこにこ、それはもう楽しそうに成島は言う。一方、遠山は心底うんざりした顔をしている。こんな風に感情を表に出す遠山はとても珍しいと思う。
「まあ……だから……出かける口実があるのは……ラッキーだよね……」
いつもに比べて、いくらか眠気の覚めたような顔で言う遠山は、心底そう思ってるんだろう。それに、すぐ外へ出てきてくれるから、結果としては俺たちにとってもラッキーなのかも 。
「でも……俺まで宿題やらされるのは……謎なんだけど……」
ブツクサつぶやいた遠山の声は、全く理解できない、という響きを帯びていた。仁羽が強い言葉を吐き捨てる。
「お前だけ免除されるわけねえだろ。宿題は学生の義務だ。さっさと片付けろ」
言った仁羽は、肩から掛けたバッグの中からワークとか原稿用紙、ペンケースなんかを取り出して遠山に向かって放り投げた。何か鞄膨らんでるな、と思ってたけどそんなもの入ってたのか、というのと。
「え、まさか仁羽、遠山の宿題持ってきたの?」
「コイツ回収するついでに持ってきたんだよ。こうでもしねえとやらねえだろうが」
仁羽は、遠山の家に寄ってから来たのだという。「ちゃんと連れてきてね!」と成島に言われたのもあるけど、放っておいたら絶対時間通りに来ないだろうと判断したかららしい。宿題の回収も目的の一つだったみたいだ。
「待たされるくらいなら引き摺っていったほうが早いしな。それに、絶対宿題やってねえだろうから、必要なもんは持ってきた」
仁羽ってば実はめっちゃ面倒見良いよな、さすがだ、と思ったら成島も同じことを考えたらしい。ぱちぱちと手を叩いているので、俺も同じように拍手を送った。
「別に大したことじゃねえよ」
ふん、と鼻を鳴らして仁羽は言うけど、俺たちは「すごいよな」「偉いよね」と口々に感想を漏らす。仁羽はちょっとだけ照れくさそうにしたあと、きっぱりと言った。
「それに、遠山をしごくいい機会だからな」
爽やかな笑顔だったけど、禍々しく見えて仕方ない。なるほど、宿題をやらせるという名目で遠山に厳しく指導しよう、という魂胆なのか。普段の仕返しを含むというか、仕返しついでに宿題やらせようって感じかもしれない。
「……別に頼んでないんだけど……」
「さっさと始めるぞ」
ぶつぶつと不服そうに遠山は言うけど仁羽は聞いてない。ただ、そもそも遠山が宿題の内容を把握していなかった。結局仁羽が内容を説明しているので、俺は成島に下描きを差し出す。アドバイスを頼むと、しばし絵を見つめてからゆっくり口を開いた。
「んー、このまま着色しちゃって平気かなぁって思うけど」
「え、いいの? これで?」
美術の宿題テーマは「郷土の風景」。近所を歩いて撮ってきた写真(川の向こうに森と山がある)を選んだけど、下描きの段階で下手さがわかる。俺には難しすぎるレベルなのかも、いっそ題材から変更したほうがいいとか言われるかも、と覚悟して、写真は全部持ってきていた。だから、このままでオッケーと言われたのは意外だった。
「もっとこう、欄干の模様とか幹の感じとか、細かい所きちんと描いて写真に近づけないと駄目じゃないの?」
下描きわりと真っ白なんだけど、という気持ちで思わず聞き返すと、成島はにっこり笑った。
「下描きの段階でそこまで細かく描くと、色塗る時大変になっちゃうよ。描き込むとしても、模様まではいいかなぁ。形がわかれば充分だと思うよ」
言われてみるとそんな気もしてくる。そういえば、下描ききっちり描いたあとに色塗ると黒くなっちゃうとかあるしな。
大体、「こうしたい」っていうものがあるわけでもないし、どうしたらいいか全然わからないのだ。
「あ、でも園田が描きたいように描いていいんだよ。僕はこう思うっていうだけだから」
「いやいや、アドバイスはありがたく受け取ります」
恭しく言えば、成島も真剣な顔でうなずく。いつの間にか取り出したメノウ様を握りしめて、重大な任務でも言い渡されたみたいな雰囲気だ。
「それじゃ、メノウ様にもアドバイスもらうね! 色の塗り方とかはね、メノウ様が詳しいから」
「メノウ様、芸術方面にも才能あるの?」
「メノウ様はすごいんだよ!」
きらきらとした笑顔の成島は、メノウ様の芸術的才能について流れるように語りだす。いつものことだし、案外面白いのでそれとなく聞いていると、前より細部が詳しくなったような気がする。自由研究の成果なのかもしれない。
そんなことを考えている俺の前では、仁羽と遠山が宿題に取りかかっていた。果たして遠山は片付けるつもりがあるんだろうか、と思ったけど、抵抗するほうが面倒だと判断したらしく、なされるがままになっていた。
成島も気づいたらしく「頑張ってるねぇ」とにこにこ笑っている。宿題に取り組む遠山というのは中々珍しいので、ついつい眺めてしまう。
仁羽と遠山は、まず作文を仕上げることにしたらしい。「とりあえず規定枚数埋めれば良し」という点では一致したようで、遠山はのろのろと原稿用紙に向かっている。
「読む本は別に決まってねえからな。覚えてる内容で書け。今さら読み直す時間もねえし、結末まで覚えてればそれでいい」
淡々と告げる仁羽の言葉を聞いているのかいないのか、遠山は無言でペンを動かしている。仁羽はそれを確認しながら、さらに言葉を続ける。
「読書感想文なんざ、適当な構成にあてはめておけばどうにでもなるんだよ。最初に書くのは、手に取ったきっかけと読む前に予想してた内容だ。次にあらすじを書いて、そこから印象に残ったシーンを二つくらい選べばいい。最後は、適当に日常生活と絡めた感想でも書いて、最初の予想からどう変わったかをまとめて終わりだ」
読書感想文に苦しんでいた俺に対するアドバイスと、同じことを遠山にも告げている。俺もこのアドバイスのおかげで、サクサク進んだのだ。あとでもう一回仁羽にお礼言おうかな、と思ってたら、遠山が手を止めた。
「桃太郎のあらすじってなに……? 鬼倒す話……?」
「桃太郎で書いてんのかよ」
仁羽の突っ込みに俺も内心で同意する。桃太郎で読書感想文ってどういう感じなんだろう……。遠山は仁羽の言葉に怪訝な顔を浮かべて「結末まで覚えてる話なんてこれくらいだし……」とつぶやく。仁羽はしばらくマジマジと遠山を眺めていたけど、気を取り直したらしい。
「まあ別に構わねえけど、あらすじはなるべく長く書いておけばいいだろ。規定文字数が埋まる」
「なるほど……」
遠山にしては珍しく、素直に仁羽に同意する。さっさと終わらせてしまいたらしい。まあ、作文面倒だもんな……。
遠山は黙々と原稿用紙を埋めていて、仁羽はそれをのぞきこんでいる。時々「キビダンゴのくだりそこまで要らねえだろ」とか「鬼のディテール追求すんな」とか言ってるけど、その度に遠山は「俺の読んだ桃太郎はこういう話だった……」と言い張っていた。
「――じゃあ園田、色塗りしちゃおう!」
成島の言葉で我に返る。そうだった、二人に気を取られてたけど俺もちゃんと終わらせないと。
「影はこっちの橋の所と右の木はもうちょっと入れてもいいかなぁ。あとは、光が右側にあるってことだけ意識して、それ以外は色塗る時に気をつければ大丈夫だと思うよ!」
ものすごく真っ当なアドバイスをくれて、 これなら絵も完成できそうな気がする。成島は、考え込みつつさらに助言を続けた。
「色塗る時はね、大きい所からにするといいよ。空とか川とかかな。あと、一回で終わりにしないで、何回も濃淡つけて塗ると立体に見えるよ! ね、メノウ様!」
手の中のうさぎに声を掛ければ、あみぐるみがこくこくとうなずく。真面目に役立つアドバイスばっかりくれるので、思わず顔の前で両手を合わせた。
「マジでありがとう。成島とメノウ様のおかげでちゃんと描ける気がする……!」
どうにかなりそうな気がしてきた俺は、よし、と気合を入れて画用紙に向き直る。成島はメノウ様と一緒にエールを送り、遠山と仁羽は原稿用紙を前に言い合いをしていた。
宿題は案外順調に片付いた。昼過ぎに集まって、ほとんど休憩なしでやってたからかもしれない。
成島のお母さんはお菓子とかジュースを何度か差し入れしてくれたけど、「食ったら作業に戻れ」「無駄口叩いてる場合か」と容赦なく仁羽に言われるので、強制的に進まざるを得なかったっていうのが大きい。
「――これで終わりか?」
英語の長文に付き合っていた仁羽が、最後の単語を書き終えた俺に尋ねる。俺はパラパラとワークをめくり、一応全てに答えていることを確認して、うなずく。
「うん。ありがとー! 隣でビシビシ突っ込んでくれるから、思ったより早く終わった……」
「お前はいちいち、全文日本語に訳そうとするから詰まるんだよ。趣旨だけわかればきちんとした日本語になってなくてもいいだろ。必要性の有無を見極めろよ」
「頑張ります……」
にらみをきかせられながら問題を解くのは、心臓には悪かったけど速度は相当だったと思う。まあ、間違えると仁羽の雰囲気が悪くなるから答えを予想しやすいっていうのと、聞いたらわりと教えてくれるからっていうのもある。
「遠山も大体終わったよ!」
明るく告げる成島は、遠山の風景画を担当していた。俺が撮った写真の中から、「なるべくシンプルなもの」を選んだらしい。青空を背景にして立つ信号機が一本。どこかの交差点の写真から、一点をズームしたらしい。使ってる色が五色くらいしかない。
「……風景画かよ、それは」
「景色なんだから合ってるでしょ……」
答える遠山はぐったりしていた。確かに、遠山にしては活動時間が長い気がする。お疲れ様、と心からのねぎらいを送った。
「読書感想文と、税金の作文もやったんだろ?」
「税金の作文っつーか、あれはほぼ辞書の抜き書きだぞ」
仁羽が呆れた調子で言葉を落とす。
成島に「辞書貸して……」と言っていたので何かと思ったら、税金に関する単語をひたすら調べて書き写し、それぞれに対する感想を書いていく、という手法で原稿用紙を埋めていたのだ。遠山は無表情で「マス目は埋めたよ……」と答える。
「それに……数学のワークも終わらせたし……」
ぼそり、とつぶやくので、いつやったんだろうと思ってたら、遠山は淡々と答えた。
「園田のワークあったから写したよ……」
「いつの間に!?」
思わず声に出ていた。持ってきてるって言ってないのによく気づいたなっていうか、いつの間に写してたんだ。目ざといというか何というか。仁羽は刺々しく「自力で解けよ」と言っているけど、遠山が気にするはずもなかった。
「じゃあ、だいぶ終わったねぇ」
「まだ残ってるけどな」
「いや、でも、遠山がこれだけ宿題終わらせてたら先生びっくりするんじゃない?」
一つも提出しないと思われてる可能性が高いだろう。全部じゃなくても、半分くらいは終わってるとか奇跡かと思われそう。仁羽は俺の言葉に舌打ちをして「甘やかすなよ」とつぶやいた。
「あ、それなら自由研究、花火にすればいいんじゃない? どの花火が一番面白いかって!」
「炎色反応とかあるだろ」
仁羽がぶつくさ言うが、当の成島は全然気にしないで明るく言い放つ。
「園田の宿題終わったし、これで花火できるね!」
きらきらとした輝きを目に溜めて言い切った。完全にやる気に満ちあふれているし、俺も異論があるわけじゃない。そうだ、夏休みの宿題は全部終わったんだ。じわじわと実感がわいてくる。
「だよな。じゃ、早くやろうぜ」
ワクワクした気持ちで呼びかける。夏休みが終わる前に宿題が片付くなんて初めてだ。ずっと作業し通しで頭も使ってたから疲れてたけど、そんなのは一瞬で吹き飛んだ。これで、みんなで花火が出来る!
花火の会場は、成島家の裏庭だった。
家の裏手に面している庭は、和室の前に設置されたウッドデッキを通って直接出ていけるようになっていた。室内の明かりで照らされるのは、所々に草の生えた土の地面や、その向こうに広がる木々。
物のない庭はだだっ広くて小さな公園みたいだし、周りの木立も成島家の敷地だという。隣の家と距離もあるから、ちょっとくらい騒いでも問題はないらしくて、ロケーションは完璧って感じだった。
水の入ったバケツや着火用ライターを用意して、外へ出る。じっとりとした暑さが漂ってはいるけど、真昼に比べれば動きやすかった。
庭に下り立った俺は、空を見上げる。気づけばとっくに日は沈んで、辺りはすっかり暗くなっていた。暗い夜空には、星が輝きを散らしている。ちゃんと晴れているし、天気の崩れもなさそうだった。
「いい天気だね」
空を見上げていた俺に気づいた成島が言えば、遠山や仁羽も上を見ていた。月はまだ出てないのか見当たらないけど、夜空には無数の星が輝いている。あちこちから、小さな光が瞬いて空一面を埋めていた。
「花火にもぴったり!」
言った成島はしゃがみこんで、ガサガサと花火の袋を開け始める。地面の上にビニール袋を敷いて中身を取り出すと、「どれからやる?」と楽しそうだ。
「やっぱり線香花火は最後じゃん?」
同じようにしゃがみこんで言えば、遠山も隣に座ってぽつりとつぶやく。
「あえての……打ち上げ花火からとか……」
「打ち上げ花火は入ってねえよ」
中身を確認していた仁羽が突っ込みを入れた。そうか、打ち上げ花火はないのか。まあ、危ないしな。納得している横では、成島が一生懸命花火を選り分けていた。
「これがいいかな! 花びらみたいなのがついてて、メノウ様にピッタリ!」
先端にひらひらした紙のついた花火を掲げるので、「うん。いいと思う」とうなずく。成島は俺の言葉に満足そうに笑ってから、周囲を見渡して尋ねた。
「えっと、ライターは誰が持ってるんだっけ ?」
「俺……」
成島の言葉に手を挙げたのは遠山だった。その手には、柄の長いライターがしっかり握られている。仁羽が眉をしかめて「一番持たせたらいけないやつが持ってねえか」とつぶやいた。いやまあ、遠山もさすがにそこまで危険なことはしないだろう。たぶん。
「はい、これみんなの分!」
成島が同じ種類の花火を手に取り、それぞれに配る。みんな大人しく受け取り、遠山が手にしたライターで火を点けようとしたんだけど。
「この紙の所千切らねえと、火薬部分に点火しねえぞ」
ひらひらした紙を千切りながら仁羽が言うので、思わず「そうなの?」と問い返した。
「てっきり、ここに火つけて燃やすんだと思ってた。導火線的な」
「先っぽだし、ここにつけるよねぇ?」
めいめい言いながらも、仁羽が言うならそうなんだろうなーというわけで、紙の部分を千切る。仁羽は「注意書きに書いてあるぞ」と言っていた。ちゃんと読んでる所が仁羽だよな。
「わあ、ついた、ついた!」
遠山に火を点けてもらった成島が、嬉しそうに叫ぶ。手に持った花火の先端から火が噴き出し、一気に周りが明るくなる。火薬の匂いが漂ってくる。
「おお、結構煙が……」
俺の花火にも火が点いたけど、思ったよりも煙が出る。慌てて風下を探して移動したら、その間に花火の勢いが増した。
「え、意外と火出るな!?」
もっと落ち着いた感じかと思ってたけど、想像以上に火に勢いがある。シューシューと音を立てて燃える火花は、見ているだけでも楽しかった。仁羽も「よく燃えるな」とか言っていて、その顔は花火に照らされているからって理由だけじゃなく、明るかった。
「……園田、ちょっとこれ持ってて」
「え?」
花火が終わりかけた頃、突然遠山に肩を叩かれた。振り向けば、丁度自分の花火に火を点けたところだった。そのまま、流れるような動作で俺に着火用ライターを渡す。
「え、なんで?」
別に構わないけどどんな理由が、と思ったら遠山が笑った。爽やかな月の光のような笑顔じゃなくて、百パーセント悪だくみしている顔だった。
「ちょっと邪魔だからね……」
一言告げた遠山は、普段からは想像もできない軽やかさで動いた。花火を前方に掲げたまま、さっと仁羽の背後に立ったのだ。真後ろで花火が燃えれば仁羽もすぐに気づく。振り返って叫んだ。
「花火を人に向けるな!」
「たまたま前方に仁羽がいるだけだよ……?」
心外な、という顔をする遠山の釈明に、もちろん仁羽が納得するわけがなかった。
「お前がその気ならこっちにも考えがある」
燃え尽きた花火をバケツに放り込んだ仁羽は、そのまま別の花火を手に取る。俺が持つ着火用ライターを奪い取り、手際よく火を点けるとまた俺の所にライターが戻ってきた。
丁度よかったので成島と俺の花火に火を点ける。しゅわしゅわと新たな火の粉が散った。五段階で色が変わるらしいから楽しみだ。
ライターはとりあえずウッドデッキに置いておいて、赤から青へ変わる火花を見つめていると、思い切り仁羽が吠えた。
「たまたま、俺の前に遠山がいるだけだからな!」
仁羽が手にしている花火は、さっきとは別物だった。遠山が前方に勢いよく噴き出す花火なら、仁羽のは四方八方にバチバチと火花を散らすやつだ。
「これでも食らえ!」
遠山に向かって仁羽が一歩踏み出せば、手元の花火もあちこちに火花を咲かせながら一緒に移動する。遠山はのらくらとそれを交わしつつ逃げ回っている。花火を持ったままの鬼ごっこみたいだ。良い子は絶対に真似しちゃいけない。
「楽しそうだねぇ」
しばらくの間二人を見つめていた成島が、自分と俺の新しい花火に火を点けながら のんびりとつぶやく。
俺たちの視線の先では、 両手に花火を持った二人がやりあっていた。あれもう、花火を楽しむっていうか武器として使っている気がするんだけど。
先に燃え尽きたのは遠山だ。その隙を仁羽が見逃すはずもない。ニヤリと笑ってそのまま突っ込んでいこうとしたところで、遠山がこっちにやってきた。花火を平和に楽しんでいる成島と俺の横をすり抜けて、別の花火を手に取る。
「あんまり無茶しないようになー」
「怪我には気をつけてね!」
俺たちの言葉にこくりとうなずき、ウッドデッキのライターを使って点火して去っていく。仁羽も同じようなことをやっているので、二人は花火を手に持ったまま応戦し合っていた。
「あー、終わっちゃった」
成島が燃え尽きた花火をバケツへ入れる。俺の花火も終わってしまったので同じように入れて、残りの花火へ目を向ける。あとは線香花火と筒状のものが一つ。減りが早いのは、楽しむとかではなく攻撃用として使っている人間がいるからの気がする。
「園田、こっちの花火はどういうのか知ってる?」
筒状のものを指して成島が言うので、俺は記憶を探りつつ答える。
「えーと、地面に置いて火点けるんだよ。こう、上に向かって花火が噴き出すの」
言いながら筒を手に取り、注意書きに目を通す。
形的にはこのまま打ち上げられそうな感じだけど、火花が出るだけのタイプのやつだ。ただ、点けたらすぐ離れたりとかしなくちゃだから、注意が必要なのは打ち上げ花火とあんまり変わらないかもしれない。
成島は俺の言葉に「面白そうだねぇ」と目をきらきらさせている。残りはもう線香花火だけだし、そろそろこれをやってもいいんじゃないだろうか。そう思ったのは成島もだったらしい。
「二人とも、これやろー!」
いつの間にか取り出したメノウ様を手にした成島がそう叫ぶと、遠山と仁羽がこっちを見た。あちらも花火は燃え尽きたようで、白熱した言い合いになってたみたいだけど、ひとまず声は届いたらしい。俺たちの所に合流すると、遠山がぼんやりつぶやく。
「……何それ……」
「えっとね、しゅわーって花火が出るの!」
「噴出花火っていうらしいよ」
遠山の言葉に成島が答え、俺も注意書きを読んで得た知識を披露する。仁羽が「ああ、手持ち以外にも入ってたな」と言うので、最初からセット内容は理解していたらしい。
「あとは線香花火だけだから、この花火やろ! メノウ様に見せるの!」
胸元にメノウ様を掲げて、成島が言う。誰からも反論はなかったので、裏庭の真ん中に筒を設置することにした。
作業が終わると、遠山が無言でしゃがみこんで、持ってきたライターで導火線に火をつけようとした。すると、成島が叫んだ。
「遠山、カウントダウンしなくちゃ! だからまだつけちゃだめだよ!」
夜空にまたたく星より強い輝きを目に散らして、成島は告げる。使命感さえ漂っているような雰囲気で「五!」とか言っているので、俺も気合を入れる。遠山はとりあえず手を止めて、成島の声を聞いているみたいだ。
「四!」
タイミングを見計らって俺も一緒にカウントを取ると、成島がにっこり笑った。俺もつられて笑顔になる。くすぐったい気持ちで深呼吸をする。
「三!」
二つの声が合わさって、夜に響く。成島が強い声で、「ほら、仁羽と遠山もだよ」と言っているから俺も「そうそう」とうなずく。
「二!」
少し遅れて、不機嫌そうな声とぼそぼそとした声が加わった。成島が目をきらきらさせているし、俺の唇にはさっきよりも深い笑みが浮かぶ。
「一!」
成島の弾んだ声、仁羽のぶっきらぼうな声、遠山の聞き取りにくい声。そこに俺の声を重ねて、最後の数字を口にした。
「ゼロ!」
遠山が導火線に火を点けて、花火から離れた。その瞬間。
地面に置いた筒の先端から、勢いよく火花が噴き出した。さっきの手持ち花火なんて目じゃない、放水してるのかってくらいの勢いで、音を立てながら火が上に向かっていく。夜の中に、オレンジ色の洪水があふれ出す。
「わあ、すごーい!」
火の照り返しを受けた成島が叫び、メノウ様も同じ色に染まっている。俺も思わず叫んだ。
「結構高さあるな!」
あちこちに火の粉を散らし、噴水みたいに花火が噴き出す。煙と火薬の匂いがする。筒の周りにも点々と火が落ちるし、顔が熱い。
「……火力すごいね……」
「これ持ってるやつが一番じゃねえか」
遠山と仁羽のつぶやき通り、花火はバチバチと音を立てて燃え上がり、火花を四方に散らしている。それがきらきらしていて綺麗なんだけど、この二人の場合どっちかっていうと。
「完全に武器としての発言だけど!?」
思わず突っ込んだ。花火が綺麗って感想じゃないし、この二人にとっての花火とは一体。
「あはは、きれいだし豪華だねぇ。ねえ、メノウ様」
成島は俺たちのやり取りなんて一切気にせず、メノウ様に語りかける。どうやら、メノウ様に盛大な花火を見せることができて満足らしかった。
高く噴き上がって火の柱を作る様子は迫力があって、夜に散る火の粉は綺麗だった。まるでここに星が落ちてきたみたいだ。音も光も盛大で、何かを祝うみたいに大きな火の花が咲いている。
ただ、勢いよく噴き出す花火は、弱まるのも早かった。火が小さくなったな、と思ったらあっという間に花火は縮んで、瞬く間に燃え尽きてしまった。
さっきまで、バチバチシューシューと音がしていたせいか、やけに辺りが静かに思えた。虫の鳴く声や、遠くで車の通る音はしているのに、まるで何も音がしないような。
「――あとは線香花火だけだね」
落ち着いた声で言った成島は、メノウ様を胸ポケットに入れる。それから線香花火に手を伸ばすので、俺たちも何となく成島に続いた。しゃがみこんで、円形になる。
遠くで虫の声が聞こえる。さわさわと木々が揺れる。音の遠い夜の中、遠山が無言で一人ずつ火を点ける。
線香花火は火の玉を作り、それから静かに辺りに火の粉を散らしてから次第に弱くなり、最後に落ちた。その様子をぼんやり眺めていたけど、ふと口を開く。
「火の玉が最後まで落ちなかったら願いが叶う、とかなかった?」
「くだらねえ」
仁羽に鼻で笑われたけど、馬鹿にしているというよりはからかっている雰囲気だった。次の線香花火に火を点けながら、まあ俺だって本気で言ってるわけじゃないんだけど、と思う。
「僕は線香花火じゃなくてメノウ様にお願いするよ?」
点火された線香花火を持つ成島が言い、遠山もぼそぼそとつぶやく。
「線香花火って……願いごと叶えるくらいの……力強さがないよね……」
この勢いで願いを叶えるって言っても効力薄そう、という顔で手元を示す。俺は苦笑を浮かべるしかない。確かに勢いという点ではささやかだけど、線香花火って不思議な雰囲気もあるし。
「園田は、何か叶えてほしいことあるの?」
ぱちぱち、と夜に散る光をまといながら、純粋なまなざしで成島が尋ねた。俺は茶化すような答えを返そうとして、口をつぐんだ。気づけば仁羽も遠山も、瞳に光の粉を映しながら俺を見ていた。
願いごと、と思う。叶えてほしいこと、こうだったらいいな、と思うこと。考えようと思えば、くだらないことから大層なものまで色々思いつくことはある。だけど、俺が本当に叶えてほしいことが何かって言ったら。願いが叶うよって言われたら、懸けてしまう言葉は――。
考えていたら、手に持っていた線香花火の火の玉が落ちた。すかさず成島が新しい線香花火をくれた。燃え尽きたのは仁羽が回収してバケツに入れてくれて、ライターを持っていた遠山は火を点けてくれた。
線香花火の先端に、火の玉ができる。ふるふると震える様子を見つめながら、俺は口を開く。
「――来年もまたみんなで花火がやりたい、かなぁ」
今日のことを思い出す。突然成島から電話がかかってきたこと。みんなで宿題をやったこと。夜空に散らばる星のこと。花火を持って応戦していた二人。勢いのある噴出花火。線香花火をみんなでやったこと。
何でもない日の、どうってことない数時間だ。思い返したらほんのちょっとだけの、他愛もない時間だ。だけど、きっと遠いいつかに今日を思い出す。
ぱちぱちと火花が散る。夜に咲く、ささやかな光の花。小さくて忘れてしまいそうで、だけど確かにここにある。ここで光を放っている。四人でこの光を囲んでいたことを、きっといつか思い出す。
「――くだらねえ」
ぼそり、と仁羽が言った。弾かれるように顔を見ると、心底呆れた顔をして言う。
「そんなもん、わざわざ願ってんじゃねえよ」
「……まあ、それってほとんどただの予定だよね……」
仁羽の言葉に遠山も同意して、二人は「スケールが小せえんだよ」とか「願いごとの定義からズレるんじゃない……」とか言っている。
「来年も、宿題終わってなかったらみんなでやって、それから花火しようね!」
成島が勢い込んで言うので、思わずうなずいた。何かを言おうと思ったけど言葉が見つからなくて黙っていると、仁羽が厳しい顔をして口を開く。
「っつーか園田、来年はさっさと宿題片付けろよ。また来年も同じことやってるんじゃねえ」
「俺は来年も……園田のワーク写すから……それは終わらせておいてほしい……」
「自力でやれ!」
やりあっている二人を眺めていたら、成島が横から「園田、それ火消えてるよ」と言う。思わず手元に目を向けると、確かに俺の線香花火は燃え尽きていた。
「……」
消える所をちゃんと見ていたわけじゃないけど、もしかしたら、火の玉は落ちなかったのかもしれない、と思った。
だって三人は、来年も一緒に花火をやるんだって言っていた。この三人がそう言うなら、それはもう決定事項に違いない。俺の願ったことは、もう叶ってしまうのかもしれない。
いつか今日を思い出すと言える日があると、俺は知っている。
たとえば終業式の夜、学校で過ごしたこと。たとえば今日、宿題をそろって片づけたこと。たとえば今日、みんなで花火をやったこと。
そういう些細な瞬間は、小さくたって確かな光を宿す。夜空に散る星や、線香花火の光みたいに。
俺は一つ深呼吸をして、三人へ視線を向ける。線香花火は残っているし、まだまだ終わりってわけじゃない。
「じゃあ、次はお前らの願いごと叶うように、線香花火やろう」
そう言って差し出すと、三人が線香花火を受け取る。遠山がライターで火を点けて、辺りに静かな火の粉が散る。小さくて、だけれど確かな明かりが灯る。
俺はその光景を眺めながら思う。
いつかきっと、この夜が未来を照らすのだ。
終わり