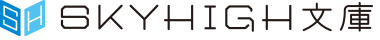シャーベット・ゲーム オレンジ色の研究 立ち読み
入り口のガラス扉を押し開けてコンビニの店内に入ると、ひと足早い冷房のひやりとした空気に全身を包み込まれた。湿り気の残る外の空気が流れ込まないようにすぐに扉を閉める。
右側にレジカウンター、左側に陳列棚という構造は自宅付近の店舗と同じだ。商品の配置もよく似ており、文房具の類はおそらく窓側から二列目だろうとふんで向かうと、やはりそのとおりだった。しかし、目的のノートの在庫は一冊もなく、その箇所だけ白い棚板があらわになっていた。
私は所在無く、そのままコンビニの中をぐるりと一巡した。
それほど広くはない店内に、客は三十歳くらいの男性がふたりと、就職活動中とおぼしきスーツ姿の女性がひとり、窓際の雑誌コーナーには女子高生らしき私服の二人組と、もうひとり。
私の目はその「もうひとり」のほうの、制服の女子高生に釘づけになった。
見慣れた茶色のブレザージャケットに、濃い緑色を基調にしたタータンチェック柄のスカート─我が朝霧学園の制服だ。
それをアレンジもせず、標準仕様で着こなしている。
つまり彼女は我が校の生徒であり、さらに言えば、この日曜模試の日に制服を着て登校する奇特な生徒でもあるという証しだ。
しかし、私が彼女に目を奪われたのはそのことだけではなかった。
彼女は、小さく雑多なごくありふれたこの町の、ごくありふれたコンビニの中にあって、明らかに異質な雰囲気を醸し出していた。
背はすらりと高く、長くつややかな黒髪はぴんと張った背筋にきちんと寄り添って微動だにしない。脇はきゅっとしまり、白い手に持った雑誌は胸の位置にまるで書見台のようにかっちりと固定されている。スカートから伸びた細長い脚と靴下の先にある革靴の両かかとは、ぴったりくっついている。
思わず、ここは表彰式やスピーチコンテストの会場ではないはずだと、あたりを確かめそうになってしまうくらいだ。
あるいは、剣道の試合で「始め!」の合図がかかる一秒前のあの雰囲気。
ひとことで言えば─―そう、凜とした空気感。
ともかくどう見ても、女子高生がコンビニで立ち読み、という本来ならよくある光景のイメージにそぐわない。すぐ左ではしゃぎながらファッション雑誌に興じているふたりとは、透明な、分厚いプラスチックの仕切り板で区分けされているようですらある。
何年生だろう─―。
二年生ではない。日曜模試の日に制服で来るような生徒はざっと頭の中に浮かぶが、その誰でもない。おとなびた雰囲気からして三年生かもしれない。
私は何気なしを装って彼女の右隣に立った。週刊情報誌を手に取りながら、彼女の白いシャツの襟元を確認する。朝霧学園の制服は学年でタイの色が違う。三年生なら青色のタイ、もし緑色なら一年生だ。
しかし、ぴしりと糊のきいた襟に丁寧に結ばれているそのタイは臙脂色─二年生の色だった。
「えっ、嘘……」
しまった─―。
思わず出た言葉にあわてて口を押さえたが遅かった。
その声が聞こえたらしく、彼女がくるりと顔をこちらに向ける。
私は言葉ごと息を呑んだ。
きりりと切り込んだような涼しい目。すうっと通った鼻のライン。意志の強さを感じさせる薄く淡いくちびるに、細いあご。後ろ姿が放つイメージそのままの、端整な顔立ち。
こんな女生徒が、我が二年にいただろうか。
頭の中に叩き込んである写真つきの生徒名簿を端からすばやくめくっていったが、彼女の顔が見つからない。もちろん、制服派以外の生徒の中にもいない。
じゃあ、このひとは誰─―?
もう一度生徒名簿を繰り始めたとき、その髪と同じように深い黒をした瞳が、私の顔から足元までをさっとなでるように見て動き、くちびるが開いた。
「私のことを誰だろうと思っているんでしょう、朝霧学園高校二年B組のクラス委員、和藤園子さん」
私は心臓が飛び出すくらいに驚いた。その反応に女子高生ふたりがこちらを見たほどだ。
「あ、ええと、初めまして─です、よね?」
「ええ、初めまして、ね」
「それなのに、どうして私のことを?」
私はつい単刀直入に訊いてしまった。
いくらクラス委員をしているといっても、私自身は決して目立つタイプではない。同じクラスの生徒以外に、顔や名前なんて知られているはずもない。
「職員室の廊下に名前が貼り出してあったから」
─―えっ?
私はキツネにつままれたような感じで、彼女を見つめた。
私の質問の答えに、なっているようでまったくなっていない。
彼女の言うように、今現在、学校の職員室の廊下の掲示板には、クラス委員の任命公示として私の名前も貼り出されている。彼女はやはり朝霧学園の生徒で、それを見たというのだろう。
それはそれでいいとして。
しかし、二年B組のクラス委員としての「和藤園子」という名前を知っているのと、初対面の私がその「和藤園子」であることがわかるのとでは、まるで別次元の話だ。
そもそも私は朝霧学園の制服すら着ていない。むしろ、どこかよその高校の制服と言っても通用するような格好なのに……。
「今度は、それだけでどうして私が『和藤園子』だとわかるのだろう、と思っているんでしょう」
またもや心を見透かされた私は、無意識にうなずいていた。
「それほど難しいことじゃないわ」
彼女はこちらを少し向き直って続けた。
「まず、あなたのその真新しいトートバッグには高校の教科書や参考書と折りたたみ傘が入っている。高校生が日曜日に教科書を持って出掛けるとしたら、図書館か予備校か学校よね。傘は使われた形跡がないから、雨のあがった時刻とあなたが左手から歩いてきたことを考えると、あなたがいたのはここから西へ徒歩で十五分圏内─相生図書館か朝霧学園かのどちらかに絞られる。そして靴は泥で汚れている」
私の足元をちらりと見る。
「図書館からここまでは舗装道路続きだから、そんなふうには汚れない。学校の校庭か、あるいは堤防か。よく見ると樹皮のかけらもついているから、きっと堤防の階段のものね。私の襟元を見て驚いていたのは、見たことのない女生徒が自分と同じ二年生だとわかったから。でも、普通はそれほど驚かないでしょうね。二百人もいる同学年の女生徒すべての顔を覚えているわけではないもの。だけどあなたは驚いた。同学年のほとんどの生徒を覚えているという確信と自負があったから。それから、あなたは模試を終えたばかりだというのにあまり落ち込んでもいないし、反対に晴れ晴れした様子でもない。つまり、勉強自体はあまり苦手ではなく、コンスタントにそれなりの成績を取るけれど、学年一位二位をぴりぴりと争うほどではない。私服もいたって無難で健全そのもの」
言いながら彼女はまた、誌面に目を落とした。
「成績がわりあい上位で、人並み以上に品行方正で、学年のすべての生徒を把握している立場といったら、クラス委員じゃないかなって思ったの。二年の前期でクラス委員を任されるひとは、一年のときにもクラス委員をやってその功績を評価されている可能性が高い。きっと学年の多くの生徒の顔と名前を一致させているか、少なくともそうありたいと努力している。そして、そのトートバッグに書かれている〈W〉の文字。二年の女子のクラス委員で名前にWがつくのは、B組の和藤園子さんだけ─―というわけ」
板に水の流れるような彼女の口上を聞いているあいだ、私は鼓動がどんどん速くなっていくのを感じていた。
私が二年連続でクラス委員を務めている理由や、こんな服装をしている理由は百パーセント正解とは言えないけれど、それ以外は観察と推理に基づいている。
こんなひとが同じ学年にいたなんて。
いままで自分は何をしてきたのだろう。クラス委員が聞いてあきれる。
しかし、そんなことはもうどうでもいい。
「あの─―」
私は満を持して最初の疑問をぶつけることにした。
「それで、あなたは?」
えっ、と彼女がこちらを見る。
「ああ、そうだったわね。私は─―」
そして、思い出したように胸の内ポケットから生徒手帳を取り出し、私の目の前にかかげて開いて見せた。
そこには彼女の写真があり、名前も書いてあった。
〈穂泉 沙緒子〉。
その下の英字表記は〈SAOKO HOZUMI〉となっている。やはり記憶の中にはない名前だ。
私は手帳の名前を読み返しながら、彼女の続きを待った。
けれども言葉は途切れたままだ。
待ちきれずに彼女をあらためて見ると、彼女の目線は私にではなく、窓の外にあった。
「穂泉─―さん?」
「ねえ和藤さん」
彼女は顔を動かすことなく、つぶやくように言った。
「悪いけど、自己紹介はまたあさってでもいいかしら」
「あ、うん、いいけど」
「ありがとう」
生徒手帳をすばやく胸にしまうと、彼女は手元の雑誌を新しい一冊と取り替えてそれを開き、また元の美しい〈彫像〉に戻ってしまった。
しかし、私は気づいていた。彼女の顔は誌面を向いていながらも、視線は変わらず窓の外にそそがれていることに。それも、入り口の扉の方へとゆるやかに動いている。
私ももちろんそちらを追った。
視線の先にいたのは、明るい黄色のレインコートの上下を着た男性だった。背が高くてやけに姿勢がよく、どちらかというと細身で、両手をポケットに突っ込んでいる。帽子を目深にかぶり、サングラスをしているので顔はよくわからない。サングラスは濃いオレンジ色の、スポーツ選手がするようなタイプだ。
男性は左手で扉を押し開けると、背を伸ばしたまま腰だけを直角ほどに深く折り曲げて、最敬礼のようにしながら店内に入ってきた。
よほど礼儀正しいらしい。
なのに、手はまたすぐにポケットに突っ込んだし、扉も開けっぱなし。帽子もサングラスも取らないまま、レジをちらりと見ながら通り過ぎると、奥の弁当などの列の方へ行ってしまった。
穂泉さんは誌面に目を戻していたが、彼を見ていたことは明らかだった。
「知ってるひと?」
「いいえ。でも、これからちょっとおもしろいことが起こりそう」
おもしろい……こと?
私の喉が、なぜか小さくごくりと鳴った。